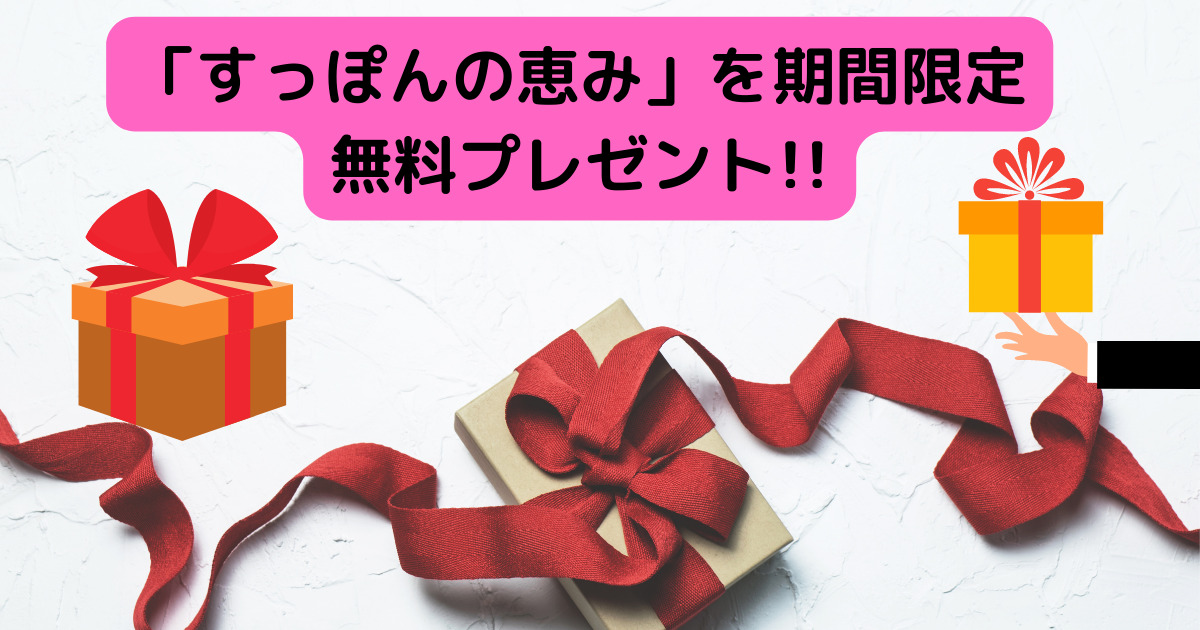![[Tags] button-only@2x 「前向きに」の、正しい活用法とは](https://theblacklinebylauren.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
「ポジティブシンキング」という言葉が流行して以来、やたら「ポジティブ」を乱発する人がいる。あまりの乱発ぶりに、その価値もぐっと下がったようだ。
私の知人のいう「ポジティブ」とは、こういうことだ。
たとえば来週までにある仕事を片づけなければならなかったとしよう。時間と必要な人手を考えると、状況は厳しいそこでだれかが「ほかの部署から応援を頼もう」といい出す。「無理して大急ぎでやっても手抜きになるといけないし、途中で何かあって順調にいかなくなることも考えられるから」と。
ここで、若い知人は口を挟む。
「どうして、できないかもしれないことを想定するわけ? 問題が起きてもいないのに、途中で何か問題が起きたらなんて、いまから考えるのはネガティブだよ。もっと前向きに、ポジティブに考えようよ」
…うまくいかなくなった場合の対策も立てて、うまくいくようにする。それがほんとうのポジティブではないのか。
うまくいかなかったときも独自のポジティブ理論を振りかざす。
「失敗はきれいさっぱり忘れようよ。ポジティブにいかなくちゃ」
過去の失敗をくよくよ思い悩んでいてもしかたがない。早く忘れて立ち直ったほうがいい…というのは、一面では正しい。しかしそれは、失敗で「学習する」ことが前提であろう。イヤなことはさっさと忘れて、たのしくやろうよというのとは話が違う。
万事にこんな調子、つまり「気分本位」なので、まわりの人たちは不安になる。また同じ失敗をするのではないか…と口にする人には、ネガティブな面を見たくない、見るのが怖い、という気持ちが強い場合が多い。
現実社会や人生にはいい面も悪い面もあるのに、いい面だけしか見ようとしない。要するに現実が見えていない。
「ポジティブ」な人は、立ち直りは早い。そのかわり、学習していないので何度も転ぶ。転んですり傷を負っている程度のうちはまだいい。
しかし大けがをしそうになったら、どうするのか。
現実を見ることができなければ、状況判断もできない。失敗したときに、「ポジティブ」といわれるばかりで痛みをわかってもらえなかったまわりの人たちが、、そのときに助けてくれるのかどうか。心配である。
![[Tags] button-only@2x 「前向きに」の、正しい活用法とは](https://theblacklinebylauren.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
【発明王エジソンの、もうひとつの逸話】
世にはびこる「偽ポジティブシンカー」を紹介する。
だれあろう、発明王のエジソンである。
エジソンがいわゆる「天才肌」ではなく、こつこつと努力を重ねるタイプであったことはよく知られているが、電球を発明したときもそうだった。
電球のフィラメントにする材料は何がいいかを探していたエジソンは、身近ものから片っ端に実験していった。
髪の毛、チーズ、紙…。発光するかどうかの実験を延々と繰り返し、試した物質は三千種類。
凡人ならここに至るまでにとっくにあきらめているところである。しかし、エジソンはこの時点で友人にあきらめろといわれても、さらにつづけた。
「世の中にはまだ二千五百もの可能性がある」
そう気分を切り替え、だからこそ、あきらめずに進めたのではないか。
いずれにしてもエジソンのこの逸話は、私たちをとても勇気づけてくれる。ひとつやふたつの挫折でくよくよしていた自分、きつい仕事にネをあげそうになっていた自分が、ばかばかしくなって、こう思えてくる。
「ふたつ失敗した。でもまだ山のように可能性は残っている」
「もう六割も片付づけた。残りはたった四割じゃないか」
挫折しそうになったときにはエジソンを思い出すといい。ここで希望を捨てたらもったいない。そう信じるための材料としてエジソンの話は大いに役に立つはずだ。
やはり、前向きな人というのは、人々にエネルギーを与えてくれる。そして、ほんとうの「ポジティブ」とは、失敗を学習して成功に近づいていこうという「行動本位」の考え方であることを、つけ加えておきたい。
![[Tags] button-only@2x 「前向きに」の、正しい活用法とは](https://theblacklinebylauren.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
【人生の岐路で、何をどう考えればいいのか】
いままでの人生で、何ひとつトラブルが起きることなく平和に過ごしてこられた、という人はまずいないだろう。だれもが何らかの形で、困難な状況に陥ったり、思ってもみなかった問題に直面したりしたことがあるはずだ。
そんなとき、落ち込み、思い悩み、挫折感を抱え、グチをこぼし、不平を漏らすのは、しかたのないことだ。むりやり感情を抑え込んでぐっと耐える必要など、さらさらない。肝心なのは、そのあとのことなのである。
たとえば会社で人事異動があり、不本意な部署に配慮されるか、遠い土地に転勤させられるか、望んでいないような地位に就かされることになった。あなたは会社への信頼感が砕け、何で自分はこんな目にあわなければならないのかと、がっくりくる。
「いったいこの私が何をしたというのだ。これまでまじめに勤めてきたではないか。会社のために働いてきたではないか。なのに、なぜこんな仕打ちをするのだ」と。
いままで何年間も専門としていた分野とはまったく違う未知なる分野にかかわらなければならなくなったときには、不安感も加わる。
「新しい仕事をきちんとやっていけるのか」
「ここへ来ての突然の方向転換はは手遅れではないのか」
「会社の中での自分の将来性はどうなるのか」
とかく不安な要素が頭をよぎる。
さて、ここが分岐点だ。ここから、人それぞれの道をいくことになる。
居酒屋で会社や人事担当の悪口をぶちまけてうさ晴らしをする人。
「こんな会社こっちから辞めてやる」と息をまく人。
「組織の一員の宿命だから」とあきらめの境地に達する人。
「やるべきことだけやって文句をいわれないようにして、空いた時間で生きがいを探していこう」と会社の外に活路を見出そうとする人。
「新しい環境で一旗揚げてやろうじゃないか」と野心をみなぎらせる人。
…人生、どれもあり、だ。人間はこうやって困難を乗り越えたり、やり過ごしたりして、つらい気持ちを徐々にに捨てていく。どれも、その人なりの「立ち直る手段」である。いい、悪い、と片づけられることではない。
ただ、そのやり方次第、立ち直りの早さ次第で、周囲の人との関係は違ってくる。グチをこぼすばかりでいっこうに自力で解決しようとしない人とあなたはいっしょに過ごしたいだろうか。新しい道を切り開こうという意志を持つ人と、あなたもいっしょに仕事をしたいのではないか。
下り坂に見える状況下でいち早く立ち直り、自力で道を切り開いていく人に、悪い印象をもつ人はいない。あなたは、どうだろうか。